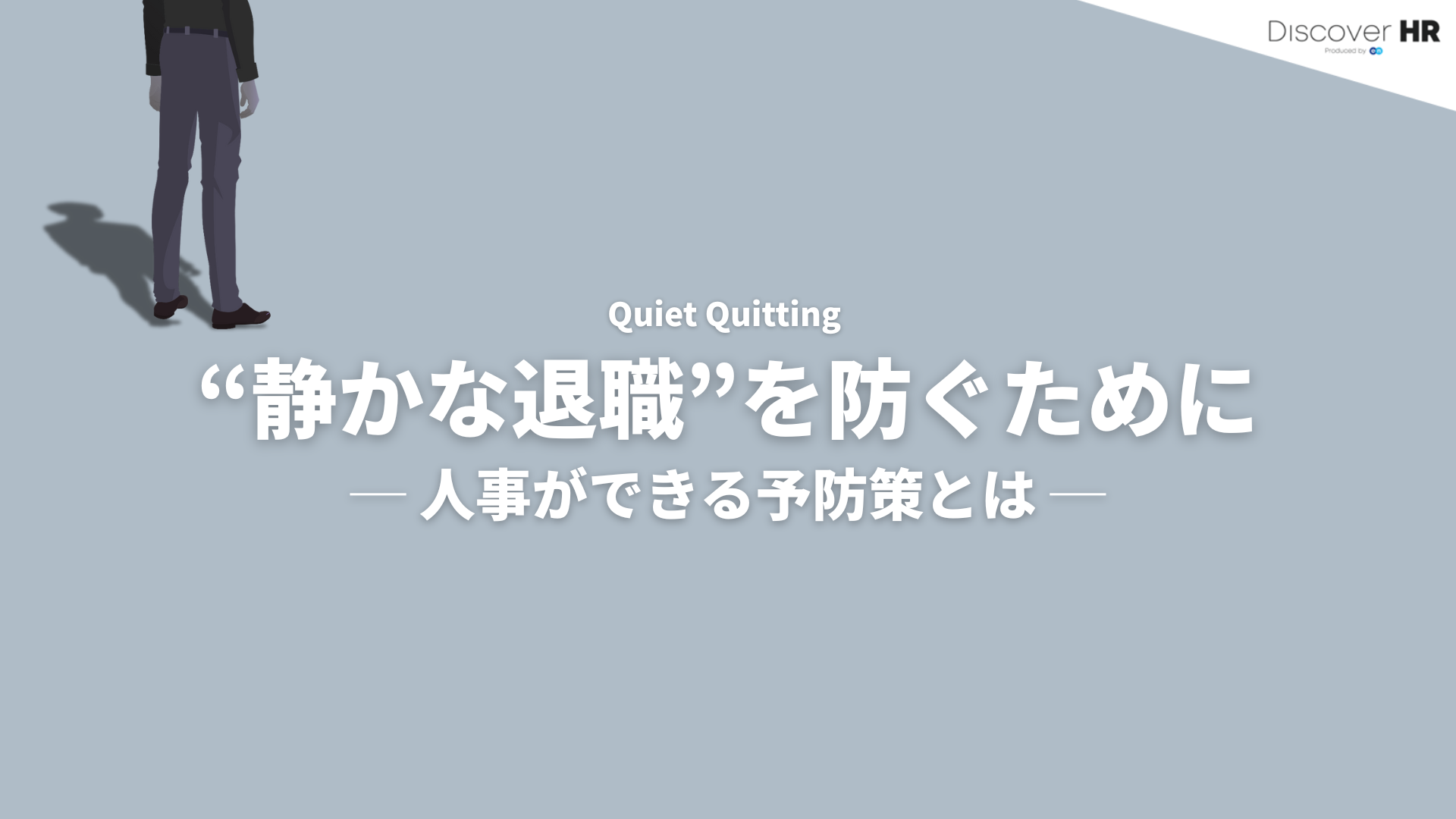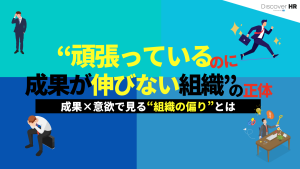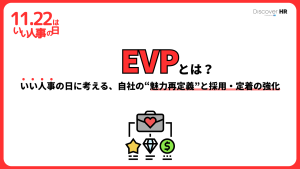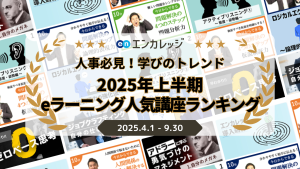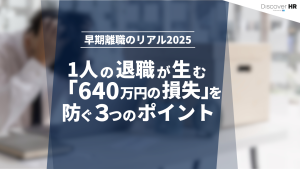現代の職場において「静かな退職」という現象が危険視されています。この現象は組織に潜在的なリスクをもたらす可能性があり、対策が求められています。今回は、この「静かな退職」の定義や増加する背景、予防策について考えてみましょう。
「静かな退職」とは
「静かな退職」とは、従業員がキャリアアップなどを目指さずに、仕事に対する情熱や意欲を失いながらも、組織内で業務をこなし続ける状態を指します。
米国を中心にトレンドになっているキーワードで、課された業務だけを全うし、それ以外の余分な業務には取り組まない、やりがいや自己実現を求めない働き方を指します。米国では「Quiet Quitting」と言いますが、日本語では「静かな退職」「がんばりすぎない働き方」と表現されます。
「静かな退職」と聞くと、社会や組織に対する強い反抗心を持っている様子を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、静かな退職者は「熱意もないが不満もない、冷めた層」を指します。経営層や管理職が「生産性向上」を叫ぶ中で、従業員は仕事にそそぐエネルギーを徐々に、静かに減らしていきます。そのため、外部には見えない形でパフォーマンスが低下していき、その影響は時間とともに拡大する可能性があります。
静かな退職者が増える理由
ひとつの働き方として広がりつつある『静かな退職』。その背景には、企業内部の要因に加え、社会全体の価値観の変化も影響していると考えられます。今回は、こうした動きが増えている原因を整理してみましょう。
企業内部の要因
1. 職務の過重
従業員が長時間労働や業務の増加によって過度に負担を強いられる場合、次第に疲弊し、モチベーションが低下します。しかし、仕事を辞めることなく業務を続けるため、従業員は徐々に退屈感や不満を抱えることがあります。
2. コミュニケーション不足
従業員が上司や同僚とのコミュニケーションを欠いている状況では、自身の意見や懸念を表明する機会が限られます。これにより、従業員は不満を内に秘めたまま業務を続け、結果的に意欲が低下していくことがあります。
3. キャリアの停滞
成長や昇進の機会が限られている場合、従業員は自身のキャリアの先行きに対して不安を感じる可能性があります。これにより、従業員のモチベーションが低下し、業務に対する関心を失うことがあります。
社会的・時代的背景
1. 働き方に対する価値観の変化
仕事中心の人生から、私生活とのバランスを重視する価値観へとシフトしています。特にミレニアル世代やZ世代では、「昇進や年収よりも、やりがいや自分の時間が大切」という意識が強まり、コロナ禍をきっかけに働き方を見直す人も増えています。
2. 社会全体の閉塞感と将来不安
将来への展望が描きにくくなっている現代社会では、「頑張る意味が見出せない」と感じる人が少なくありません。賃金の伸び悩みや社会保障制度への不安、人口減少なども不安感に拍車をかけています。
3. メンタルヘルスと自己防衛意識の高まり
職場でのストレスや燃え尽き症候群を避けるため、「あえて期待以上の成果を出さない」という選択をする人も。特に若い世代では、精神的な安全が確保されない環境に対して敏感に反応する傾向が強まっています。
静かな退職を予防するには?
静かな退職は、表面化しづらいぶん対処が遅れがちです。人事が先回りして取り組むために、効果的なアプローチと具体的な施策を3つの観点から整理しました。
1. モチベーションの向上
MBOやOKRの目標と1on1を連動させた運用
目標設定と1on1を連動させ、日々の業務と個人の成長を結びつける運用が重要です。 目標の立てっぱなしを防ぎ、上司と対話しながらキャリアと紐づけた振り返りを行います。
インセンティブ制度の導入
行動や成果が適切に報われる評価・報奨制度を整備することで、社員の意欲の向上につながります。 表彰制度・金銭報酬など、会社文化に合った仕組みを設計することが効果的です。
ポジティブフィードバックの強化
チャットツール上に「称賛チャンネル」を設け、感謝や賞賛を日常的に可視化することで組織文化の醸成に繋がります。
2. コミュニケーションの強化
1on1ミーティングの制度化と支援体制の整備
月1回の1on1を制度として運用することでコミュニケーション機会を創出します。 マネージャーには質問例や進め方のガイドを提供し、レベルのばらつきを抑える運用が重要となります。
匿名のサーベイを実施し、課題の抽出と改善
匿名のエンゲージメント調査を実施することで、率直な声を拾い上げやすくなります。 サーベイ結果は部門別にフィードバックし、課題の可視化と改善施策の企画に繋げることが効果的です。
部門横断のプロジェクトワークやテーマ別対話会の実施
日常業務とは別のテーマで部門を越えて対話する機会をつくることも有効です。
例:会社の理念や課題を考えるワーク、未来の事業アイデアを出すワークなど。
3. キャリア開発のサポート
社内公募の運用
社員が自ら希望する部署に異動できる「社内公募」を制度化します。 チャレンジ機会の提供により、キャリアの選択肢と自己決定感の向上を後押しします。
スキル可視化+リスキリング支援
スキルマップを可視化し、成長領域に沿った学習を支援します。eラーニングやOJT、異動と連動させることで実務的なリスキリングに繋がります。
階層別のキャリア研修の実施
若手にはキャリアの描き方を学ぶ研修、ミドル層には再構築の機会を提供するなど、階層に応じた施策が効果的です。「これからどう働くか」を考える場を通じて、仕事への主体性を高めます。
まとめ
静かな退職は、従業員のモチベーションや意欲の低下を示す重要なサインです。組織は、適切な予防策を講じることで、従業員のエンゲージメントを高め、生産性と士気を向上させることができます。定期的なコミュニケーションやキャリア支援の提供によって、静かな退職を未然に防いでいきましょう。
エンでご支援できること
コミュニケーションをサポートする「Talent Analytics」
採用選考の見極めだけではなく、上司と部下がコミュニケーションを取る際にも活用できる適性検査『Talent Analytics(タレントアナリティクス)』を提供しています。1987年から約40年の歴史を持ち、導入企業数は24,000社を突破。ご興味があればぜひ一度無料トライアルをお申込みください。
キャリア開発をサポートする「エンカレッジ」
スキル診断で従業員の強み・弱みを可視化。1,000を超える講座から、従業員自身が何を学ぶべきか・何を学ばせるべきかがわかるeラーニング「エンカレッジ」。詳細はお問合せください。